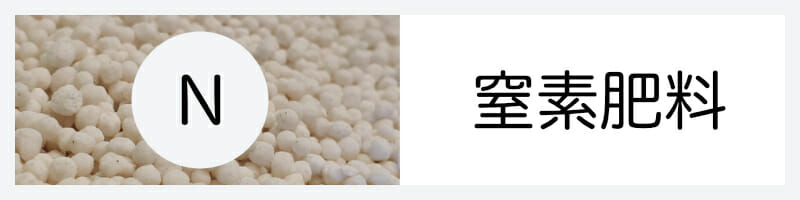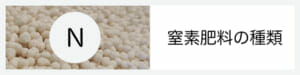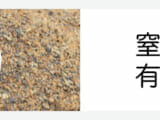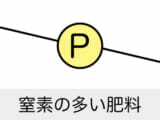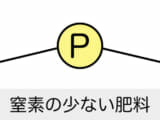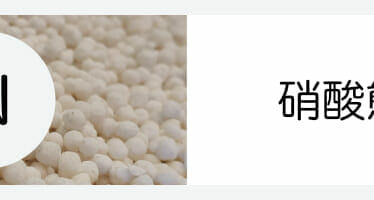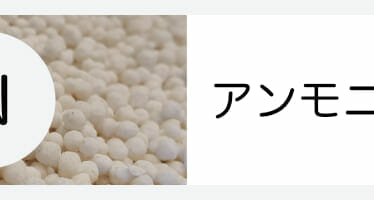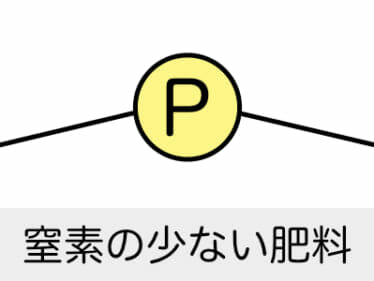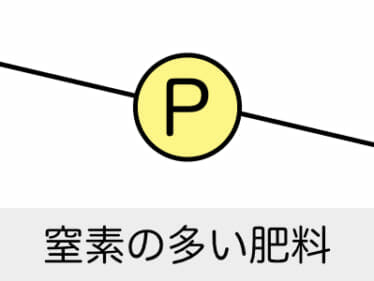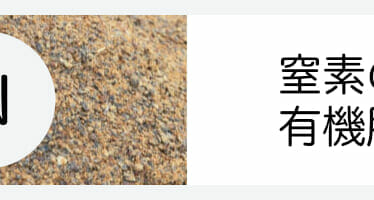作物栽培において、わき芽かきや摘芯、摘果などの手入れとともに重要となってくるのは施肥(元肥・追肥)です。特に三要素(三大栄養素)の窒素(チッソ)、リン酸(リンサン)、カリウム(カリ・加里)は植物の成長に欠かせないものとなります。
窒素とは
窒素(N)は、肥料の三要素の一つで植物の生育に最も大きく影響する要素です。光合成に必要な葉緑素、植物の体を形作るタンパク質など、植物が生長する上で重要な働きをする物質となります。窒素肥料は「葉肥(はごえ)」とも呼ばれ、生育の初期に効果的であり、茎と葉の生長に大きく影響します。
「窒素系肥料」と「窒素質肥料」は違う?
窒素肥料を探している過程で「窒素質肥料」という単語をよく目にすると思います。実は「窒素質肥料」は、肥料取締法で定義された普通肥料のうち窒素成分を保証した肥料のことを指します。
簡単に言うと、窒素質肥料には石灰窒素やIB窒素肥料、窒素が保証されている化成肥料などは含まれますが、有機肥料は含まれません。ややこしいですね。そのため、農家webでは、窒素質肥料に限らず「窒素系肥料」として、窒素が含まれている単肥、化成肥料、有機肥料を紹介します。
窒素の効果
先述したとおり、窒素は植物にとって重要な三要素(三大栄養素)の一つです。窒素が不足(欠乏)すると、植物の生長が止まったり、正常な生長を妨げてしまうことになります。
窒素は植物を形作るために必要なタンパク質、光合成に必要な葉緑素、その他細胞、酵素、ホルモン、核酸など植物が生きていく上で必要な働きをする物質の構成元素なのです。栽培においては作物の収量や品質に直結してくる非常に重要な要素です。
逆に、窒素を与えすぎることも植物にとってはよくありません。適量を必要なときに与え続けることが重要です。肥料のラベルなどには化学式や元素記号で表され、窒素全量のことを「N」または「T-N」と記述されることが多いです。
窒素肥料の種類
窒素肥料の種類を分ける場合、いくつかの切り口があります。
- 窒素質肥料(普通肥料による分類)
- 窒素が含まれた化成肥料
- 窒素が含まれた有機肥料(有機質肥料)
単肥・窒素質肥料
一番基本となるのは、肥料取締法による分類です(出典:15 肥料取締法について – 農林水産省)。
肥料取締法では、窒素質肥料は下記のように分類されています。
窒素質肥料の中でも、下記は代表的なものです。それぞれの特性に合わせて使用方法を検討しましょう。
| 肥料 | N | P | K | 肥効のタイプ | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿素 | 46% | – | – | 速効性 | アンモニアガスが発生しやすい。液体肥料として葉面散布もできる。 |
| 硫安 (硫酸アンモニウム) | 21% | – | – | 速効性 | 全量アンモニア態窒素。 |
| 塩安 (塩化アンモニウム) | 25% | – | – | 速効性 | 全量アンモニア態窒素。 |
| 硝安 (硝酸アンモニウム) | 32% | – | – | 速効性 | アンモニア態窒素16%、硝酸態窒素16%。 |
| 石灰窒素 | 20%〜21% | – | – | 緩効性 | アルカリ分を含んでいる。農薬成分シアナミドが含まれている。粒状・粉状がある。 |
| IB窒素 | 31% | – | – | 緩効性 | 加水分解。 |
| CDU窒素 | 31% | – | – | 緩効性 | 微生物分解。 |
窒素が含まれた化成肥料
化成肥料には、窒素が含まれていることが多いです。化成肥料は、 三要素のうち二要素以上を含んでいる肥料のことを指しますが、窒素にリン酸もしくはカリウム(またはその両方)を含んだ肥料が多いです。
化成肥料に含まれている窒素には、無機態窒素であり硝酸態窒素やアンモニア態窒素として土壌に溶け出します。そのため、速効性があり、効き目がすぐに現れるものが多いです。栽培作物や植物への追肥として、定期的に施肥をすると良いでしょう。
逆に、すぐに溶け出して流亡してしまう可能性も高いため、元肥としての施用や雨が続く日の露地栽培での施用は向きません。
速効性だけではなく、尿素やコーティング肥料などゆっくりと長く効く(緩効性)ような窒素が含まれているものもあります。実際に使用する肥料がどのような性質なのかは、ラベルをよく読みましょう。このような肥料の場合には、元肥、追肥どちらに使用できます。
窒素が含まれた有機肥料(有機質肥料)
有機肥料(有機質肥料)には、動物性有機肥料(魚かすなど)と植物性有機肥料(米ぬか、油かすなど)があります。有機肥料にも窒素成分が含まれていますが、化成肥料や単肥に比べると成分保証率が小さく、含有量が低めです。
窒素の施用としてよく使われる有機肥料は、魚かす(魚滓)や油かす(油粕)です。有機肥料の他に土作りとしてよく利用される堆肥(牛糞、豚糞、鶏糞など)なども窒素を含んでいます。
また、有機肥料や堆肥に含まれる窒素は有機態窒素が主であるため、無機態窒素(硝酸態窒素・アンモニア態窒素)に変わり植物へ吸収されるまで時間がかかります。そのため、遅効性肥料であることが多いです。ぼかし肥料を作って施用することで速効性を上げることもできます。
窒素が多く含まれた有機肥料についてもまとめていますので、参考にしてください。
硝酸態窒素とアンモニア態窒素の違いと吸収過程
窒素は窒素でも、形態などによって違いがあります。大まかに下記のように分類することができます。
- 有機態窒素
- タンパク態窒素
- ペプチド窒素
- アミノ糖など
- 無機態窒素
- アンモニア態窒素
- 硝酸態窒素
※主な成分のみ記載


尿素肥料に含まれる尿素態窒素もあります。尿素態窒素は、無機化合物から合成された有機化合物として非常に重要な化合物です。
アンモニア態窒素と硝酸態窒素の違い、各成分の作物への吸収過程は、以下の記事にそれぞれまとめていますので参考にしてください。
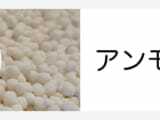
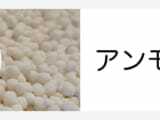
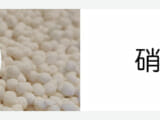
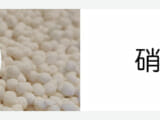
魚かすなどの有機肥料(有機質肥料)や堆肥には、窒素成分として有機態窒素が含まれています。有機態窒素の多くは難分解性(分解されづらい)ですが、易分解性(分解されやすい)のタンパク態窒素などは土壌微生物によって徐々に分解され、無機態窒素(硝酸態窒素やアンモニア態窒素)に変化して植物に吸収されるようになります。
有機肥料が遅効性肥料と言われるのは、この分解に時間がかかるためなんです。
窒素が多い/少ない肥料
窒素の多い肥料
保証成分量に記載されている成分のうち、「窒素全量(T−N)」、「アンモニア性窒素(A−N)」、「硝酸性窒素(N−N)」など、窒素と記載されているものの割合(%)が他のものと比べて高ければ、窒素の多い肥料と言えるでしょう。
化成肥料であれば、NP化成やNK化成は窒素を多く含んだ高度化成肥料として挙げられます。
窒素の少ない・無配合の肥料
逆に窒素の割合が他のものと比べて低い、もしくは全く入っていない肥料というものもあります。
化成肥料であれば、PK化成は窒素を全く含まない高度化成肥料として挙げられます。
窒素肥料の作り方
窒素の含量が比較的多い有機質を組み合わせて、ぼかし肥料とすることで窒素の多く含まれた肥料を作ることができます。
おすすめの窒素肥料
上記で解説したとおり、窒素系の肥料と言ってもその特徴や使い方は様々です。下の基準に従って、どのような肥料を購入・使用するかを絞り込んでいくとよいでしょう。最後は必ず、購入・使用する予定の肥料のラベルや資料などをよく読み、自分が使いたい方法と合っているか確認しましょう。
- 元肥として使用するのか、追肥として使用するのか。
元肥として使用する場合は「遅効性」「緩効性」の肥料、追肥として使用する場合は「緩効性」「速効性」の肥料がおすすめです。 - 土作りで酸度(pH)調整を行いたいか。
アルカリ性によせたい場合には、石灰窒素が有効です。 - 窒素肥料のみを投与したいという限定的な目的や独自での施肥設計ができる技量はあるか。
土壌診断を行い、独自(もしくはJAや肥料メーカーなど)で施肥設計ができる方であれば単肥のほうがコストを安く抑えられるので良いでしょう。 - 有機肥料のみを使いたいというこだわりはあるか。
有機肥料のみを使うということであれば、窒素成分が含まれている魚かすや油かすなどを使用しましょう。すぐに効果を現したいという場合には、ぼかし肥料も有効です。
植物の生長に必要な三要素と多量要素、微量要素について
植物が育つために必要な三大栄養素(三要素)は窒素(チッソ)、リン酸(リンサン)、カリウム(カリ・加里)です。まずはこの三要素と中量要素、微量要素について、おさらいしましょう。
窒素(チッソ)とは
窒素(N)は、肥料の三要素の一つで植物の生育に最も大きく影響する要素です。光合成に必要な葉緑素、植物の体を形作るタンパク質など、植物が生長する上で重要な働きをする物質となります。窒素肥料は「葉肥(はごえ)」とも呼ばれ、生育の初期に効果的であり、茎と葉の生長に大きく影響します。
リン酸(リンサン)とは
リン酸(P)は、肥料の三要素の一つで植物の遺伝情報の伝達やタンパク質の合成などを担う核酸の重要な構成成分となります。施肥を考える上では、「実肥」と呼ばれ、開花・結実を促すためにリン酸が必要となります。また、植物全体の生育や分げつ、枝分かれ、根の伸長など様々な要素に関わっています。
カリウム(加里・カリ)とは
カリウム(K、加里)は、肥料の三要素の一つで植物体内でカリウムイオンとして存在しています。カリウムイオンは葉で作られた炭水化物を根に送り、根の発育を促したり、植物を丈夫にして病気などに対する抵抗力を高める働きがあります。そのため、カリウム肥料は「根肥(ねごえ)」と呼ばれます。
その他の中量要素
窒素、リン酸、カリウムの三要素以外の中量要素として、カルシウム(Ca)、硫黄(S)、マグネシウム(Mg)があります。
| 要素名 | 主な役割 |
|---|---|
| カルシウム(石灰・Ca) | 葉や実の組織を作る(細胞膜の生成と強化)、根の生育促進 |
| 硫黄(S) | 酸化・還元・生長の調整などの植物の生理作用や葉緑素(葉にある光合成を担う葉緑体に含まれる)の生成に関与 |
| マグネシウム(苦土・Mg) | 葉緑素の構成元素、リン酸の吸収と移動 |
また、炭素(C)、水素(H)、酸素(O)も中量要素ですが、主に水や大気から吸収される要素です。
微量要素とは
微量要素には、ホウ素(B)、塩素(Cl)、マンガン(Mn)、鉄(Fe)、亜鉛(Zn)、銅(Cu)、モリブデン(Mo)、ニッケル(Ni)があります。三要素や多量要素と比較すると、必要な量は多くありませんが、欠乏すると様々な生理障害が発生します。
| 要素名 | 主な役割 |
|---|---|
| ホウ素(B) | 細胞壁の生成、カルシウムの吸収と転流 |
| 塩素(Cl) | 光合成(光合成の明反応) |
| マンガン(Mn) | 葉緑素の生成、光合成、ビタミンCの合成 |
| 鉄(Fe) | 葉緑素の生成、鉄酵素酸化還元 |
| 亜鉛(Zn) | 酵素の構成元素、生体内の酸化還元、オーキシンの代謝、タンパク質の合成 |
| 銅(Cu) | 光合成や呼吸に関与する酵素の構成元素 |
| モリブデン(Mo) | 硝酸還元酵素(硝酸をタンパク質にする過程で利用される)、根粒菌の窒素固定 |
| ニッケル(Ni) | 尿素をアンモニアに分解する酵素の構成元素、植物体内で尿素を再利用 |