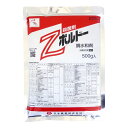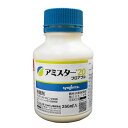葉枯病は、ネギやニンニクなどで発生し、葉が暗い褐色に変色して、やがて枯れてしまう恐ろしい病気です。
ここでは、葉枯病を予防、治療するためにはどのような農薬を使えばいいのか、その他、効果的な防除法について詳しく解説してきます。
葉枯病とはどんな病気?
葉枯病とは?
立枯病は、一種のカビ(糸状菌)によっておこります。病原菌(ボトリチス菌)は前年の被害植物上で越年します。翌春、分生胞子を生じて伝染していきます。
発病は低温時に起こりやすく、晩秋から初冬がもっとも発生しやすい時期になります。生育が良好な状態では発病しにくく、肥料が切れるなど、生育が弱った時は発病しやすくなります。
葉枯病の症状
ネギの場合は、先が枯れる「先枯れ病班」葉の中央部に斑点ができる「斑点病班」葉が黄色のモザイク模様になる「黄色斑紋病班」の3つの症状に分類されます。特に、斑点病班はべと病などの病害が発生したあとに、二次的に葉枯病菌が感染して発生しやすいため、べと病を防除することが葉枯病を防除することにつながります。
イチゴの場合は、葉に紫褐色の斑点ができ、それが暗い褐色色〜黄褐変して枯死します。




防除における、予防と治療
病原菌の中でも、葉枯病のようなカビ(糸状菌)によるものは、3段階で病気の発病させます。
- カビの胞子が葉に付く
- 付いた菌が葉の表面のワックス層を溶かして菌糸を伸ばし、植物の細胞内に吸器を作る
- 植物の細胞から栄養を取り、、分生胞子を作って繁殖し、再び胞子を拡散、増殖させる
1の段階でカビを防ぎ、2の段階に行かないように、胞子の発芽を抑制したり菌糸の侵入を阻害するのが「予防剤」で、2、3以降になり、菌糸を死滅させたり、分生胞子が作られるのを阻害するのが「治療剤」になります。
農薬のラベルには、「予防剤」「治療剤」の表記はありません。菌が蔓延した状態で完全に効く治療剤はほぼないため、「治療剤」と名乗ると、効かなかった場合にメーカーとして不利益を被るのを避けるためだと思われます。
「予防剤」か「治療剤」かは、「病気の初発後に使用しても効果が期待できる」など、発病後でも防除効果が期待できるような記載があるかどうかで判断することができます。
葉枯病に効果がある農薬
予防のため
Zボルドー、ICボルドー66D
ボルドーは100年以上前から徴用されている農薬で、殺菌剤として使われる硫酸銅と消石灰の混合溶液です。塩基性硫酸銅カルシウムを主成分とする農薬で、果樹や野菜などの幅広い作物で使用されていて、予防効果は高く、安価な点が特長です。また有機栽培でも使用可能です。
トップジンM
抗菌範囲が広く,複数病害の同時防除が可能なため,総合防除剤として活躍する農薬です。ほとんどの殺菌剤,殺虫剤あるいは殺ダニ剤と混用できるので,散布を省力化することができます。
また、速効性と残効性を有し、すばらしい効果が長続きし、 低濃度で高い効果があります。
ジマンダイセン(ジマンダイセン水和剤、ジマンダイセンフロアブル)
ジマンダイセンは、主成分マンゼブの分解物であるイソチオシアネートが、菌の生合成に必要な酵素類の不活化,ATP形成阻害,SH基の不活化などに作用し,菌体の酵素取込みやCO2放出を阻止したり原形質活動を阻害し、幅広い病害虫から作物を守る殺菌殺虫剤です。
幅広い病害虫から作物を守る殺菌殺虫剤で、特にトマト・疫病、きゅうり・べと病、きく・白さび病に優れた予防効果を発揮します。作用点が複数存在するため、薬害耐性菌の発達リスクが少ない農薬といえます。
このほか、予防薬としてシグナムWDGもおすすめです。
治療のため
アミスター20フロアブル
アミスター20フロアブルは、メトキシアクリレート系殺菌剤です。各種野菜、畑作物、茶の病害に高い効果があり、予防効果と治療効果を合わせもつ殺菌剤です。
べと病も同時防除するために、散布は葉の裏面にていねいにタップリかけることが重要です。
この他、ランマンフロアブルやアドミンフロアブルなどもおすすめです。
上記の農薬は原液を水で溶かして薄めて使用する液剤、乳剤や水溶性の粉剤、粒剤(粒状や顆粒)です。希釈方法等については下記をご参考ください。
化学的防除以外の防除方法
うね間を開けて、風通しをよくする
葉枯病にかぎりませんが、糸状菌による病害は、風通しをよくすることが防除につながります。また、草丈の低い品種を選ぶのも有効です。
病原菌の隔離および不活化
被害が出た茎葉は肥料袋などに隔離するなど、病原菌の隔離および不活化をすることが大事です。
周りをしっかり除草する
圃場の周りに雑草が多くあるとその雑草に病害虫が発生し、繁殖、促進してしまいます。圃場の周りの雑草はできるだけ除草しておくことが、被害を少なくするのに重要です。
除草については、以下のコンテンツが参考になります。(この他、イネ科雑草、広葉雑草、多年生やその他の厄介な雑草(スギナやヤブガラシ、スズメノカタビラなど))は個別の対策、防除記事もあります。


まとめ
ここで紹介した農薬は、JA販売店やホームセンターのガーデニング・資材、庭木コーナーにあるものもあります。ほ場で早期発見し、適切な薬剤や防除方法でしっかり発生を予防、ガードできると、農薬散布と言った農作業の回数を減らすことができます。
発生してからの圃場の回復は非常に難しいので、予防でしっかり防除することを心がけましょう。
若い葉や茎の表面にうどん粉をまぶしたように白いかびが生えるうどんこ病の防除は下記を参考にしてみてください。市販のベニカ、ベニカスプレーなども使えます。
(補足)殺虫剤など、他の農薬について
農家webでは、下記のような害虫別のコンテンツがあります。気になるコンテンツがあれば、ぜひ参考にしてみてください。

















栽培に役立つ 農家webのサービス
農家web 農薬検索データベース
作物に適用がある農薬を一覧で探したいときには、「農家web農薬検索データベース」が便利です。
検索機能は、適用作物・適用病害虫に合致する農薬を探す「農薬検索」、「除草剤検索」をはじめ、さまざまなキーワードで検索できる「クイック検索」、農薬・除草剤の製品名で検索できる「製品検索」、農薬・除草剤に含まれる成分名で検索できる「成分検索」の4つで、農薬・除草剤の作用性を分類したRACコードや特性、 効果を発揮するためのポイントなど実際の使用に役立つ情報も知ることができます。

農家webかんたん農薬希釈計算アプリ
除草剤、殺虫剤を代表する農薬の液剤は、かなりの割合が原液で、水で希釈して散布するのが一般的です。希釈倍率に合わせて水と混ぜるのですが、希釈倍率が500倍、1000倍と大きく、g(グラム)やL(リットル)などが入り混じっていて、計算が難解だと感じる方も多いのではないでしょうか。
「農家webかんたん農薬希釈計算アプリ」は、使用する農薬の希釈倍数を入力し、散布する面積などから薬量・液量を算出します。面積の単位や薬剤の単位も簡単に行えます。
ラベルを見て希釈倍率を入力するだけでなく、農薬検索データベースと連携しているので、使いたい製品・適用ラベルを選択することで、希釈倍数を自動入力することができます。

農家web かんたん栽培記録
作物を栽培するときに、植え付けから収穫までの栽培記録をつけることは、作物の安全性を守る他にも、ノウハウを蓄積し、よりよい作物を栽培するためにも大切な作業です。
農家webのかんたん栽培記録はこれひとつで、無料で作物ごとに栽培記録できるだけでなく、その作物に発生しやすい病害虫やおすすめ農薬、また農薬に頼らない防除方法も、簡単にカレンダーから確認することができます。会員登録すれば、LINEに予察情報も届きます。パソコン等が苦手でも、タップで簡単に作業日誌をつけられます。