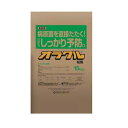根こぶ病(ネコブ病)は、アブラナ科野菜を連作すると発生する非常にメジャーな病害です。
ここでは、根こぶ病(ネコブ病)を予防、治療するためにはどのような農薬を使えばいいのか、その他、効果的な防除法について詳しく解説してきます。
根こぶ病とはどんな病気?
根こぶ病とは?
根こぶ病は、アブラナ科の植物(キャベツ、ダイコン、小松菜、ブロッコリー、白菜、チンゲンサイなど)に発生する病気です。
根こぶ病の病原菌はネコブカビというカビの一種ですが、菌糸体がなく、アメーバ状なのが特徴です。この病原菌が特殊な胞子(休眠胞子)となり、根や土壌で数年間(場合によっては10年以上)生存し、伝染源となります。この胞子は発芽して作付けされた新根、根毛に侵入し、細胞を侵し急激に増殖し、こぶができてきます。こぶは収穫期には腐敗します。
発病が起こりやすい地温は20~24℃です。また土壌のpHも発病に大きく影響し、pHが7.2以上では発病が抑制されます。つまり酸性の土壌で激発しやすいのも特徴です。
この病菌は降雨などで水の流れにのってまわりに広がっていきます。数年、ときには10年以上も土中で生き続け、伝染源になり続けるので非常に厄介な病原菌と言えるでしょう。
根こぶ病の症状
こぶができてしまうと、根っこの組織を破壊してしまいます。そして根の維管束が圧迫され、水分や養分の運搬がうまくいかなくなり、葉が萎れたり、生長が衰えて、生育不良に陥ります。最悪枯死に至る重大な病気です。

根こぶ病とネコブセンチュウの見分け方
根こぶ病とネコブセンチュウは症状が似ているため、見分けるのが困難ですが、根こぶ病は病原菌によるもの、ネコブセンチュウは線虫(センチュウ)という棒状ないし糸状の生き物によるもので、別物です。
見分け方としては、根こぶ病はアブラナ科植物にしか発生しないので、アブラナ科ではない野菜のトマトやキュウリ、サツマイモ等で症状が見られたら、ネコブセンチュウによるものだと見分けることができます。
また、ホウセンカはネコブセンチュウに寄生されやすい特徴があるため、ホウセンカを植えてみて、根にこぶがたくさんできたら、ネコブセンチュウの場合と見分ける方法もあります。
ネコブセンチュウの防除については下記をご参考ください。
根こぶ病に効果がある農薬
根こぶ病の防除は土壌に長く病原菌が生存することもあり、農薬による科学的防除の他に、様々な防除方法を組み合わせて対応していくIPM(総合的害虫管理)が重要です。
農地を取り巻く環境や病害虫の対象種の個体群動態を考慮しつつ、「生物的防除」「化学的防除」「耕種的防除」「物理的防除」を組み合わせることで、病害虫の発生を経済被害を生じるレベル以下に抑えることをいいます。
- 「生物的防除」 病害虫の天敵を導入し、病害虫密度を下げる防除法
- 「化学的防除」 化学薬剤を使用して行う防除法
- 「耕種的防除」 栽培法,品種、圃場の環境条件等を整え、病害虫の発生を減らす防除法
- 「物理的防除」 防虫ネット、粘着トラップ、光熱等を利用して病害虫を制御する防除法
(IPM・・・Integrated Pest Management)
根こぶ病の科学的防除には、土壌混和、土壌灌注などの方法で播種(は種)または定植前に土壌消毒を行うのが主流です。ここでは有効と言われている代表的な農薬をご紹介します。
クロルピクリン錠剤
クロルピクリンは、臭化メチル以外の土壌消毒方法として利用される土壌くん蒸剤です。クロルピクリンのガスは空気よりはるかに重く、土壌の下層まで拡散し、土壌中の微生物や雑草の種子などに非選択的に効果を及ぼします。
クロルピクリン錠剤は刺激臭による作業の困難性を改善するため,有効成分を錠剤化して水溶性のフィルムに包んだものです。このためハウス内でも使用できます。また、周辺へのガス放出の心配がないため、住宅近接地でも使用できます。
使い方は30×30cm毎(15cmの深さ)1錠処理が基本になります。また、ゴボウなどの深根性作物や病原菌が深層まで分布するような病害の場合には,より深い位置に処理することで,高い防除効果が得られます。
オラクル
殺菌剤オラクルは、有効成分アミスルブロムを有する、日産化学工業(株)によって開発された殺菌剤です。
有効成分のアミスルブロムとは、根こぶ病菌の休眠胞子から形成される遊走子を殺菌する効果があり、土壌中に生息する休眠胞子の密度を減らす効果があります。従来の農薬が根こぶ病の休眠胞子を眠らせたままにする(静菌作用)ところを、しっかり直接殺菌するところが最大の特長です。このため、土壌中の病原菌自体の数を低減し、予防効果を高めます。
オラクルは土壌中の休眠胞子からの遊走子を殺菌する効果が高いことから、おとり作物(根こぶ病抵抗性ダイコンCR―1等)植物と併用することで土壌中の休眠胞子をいっそう減少させ、病害防除に効果を発揮します。
また天敵や有用昆虫、環境生物に対する悪影響、薬害が少なく、様々な場面で使いやすいことも特長といえるでしょう。
ダコニール1000(FRAC M)
広範囲の病害に有効な定番の殺菌剤です。
このほか、フロンサイド(フロンサイドSC、フロンサイド粉剤)、ランマンフロアブル、ネビジン(ネビジン粉剤、顆粒水和剤、SC)、フィールドキーパー水和剤などがあります。
上記の農薬は原液を水で溶かして薄めて使用する液剤、乳剤や水溶性の粉剤、粒剤(粒状や顆粒)です。希釈方法等については下記をご参考ください。
化学的防除以外の防除方法
連作を避ける
発生が見られた時はもちろん、連作を避けるのは根こぶ病の予防に大変有効です。
pHをコントロールする
土壌全体のpHを高く維持するのは栽培上難しいかと思います。畝(うね)の定植位置に溝を切って、消石灰を施し、最初に根が伸びていく部分だけをpHが高い土にする方法で、根こぶ病を大きく減らした事例もあります。
このように根のまわりに石灰を利用して高pHにするのは有効な防除方法です。
土壌のミネラル成分を保つ
連作を避け、土壌診断を行い、バランスの良い土作りができれば、根こぶ病の発生を減少させることができます。
ライムギ、ソルゴーなどの緑肥作物をすき込む
ソルゴー、イタリアンライグラスなどを輪作し、栽培後すき込むことで、根こぶ病菌密度を下げ、有機物の補給も行うことができます。
周りをしっかり除草する
圃場の周りに雑草が多くあるとその雑草に病害虫が発生し、繁殖、促進してしまいます。圃場の周りの雑草はできるだけ除草しておくことが、被害を少なくするのに重要です。
除草については、以下のコンテンツが参考になります。(この他、イネ科雑草、広葉雑草、多年生やその他の厄介な雑草(スギナやヤブガラシ、スズメノカタビラなど))は個別の対策、防除記事もあります。




まとめ
根こぶ病(ネコブ病)は、非結球あぶらな科葉菜類などに代表されるアブラナ科野菜に発生する非常にメジャーな病害です。
ここで紹介した農薬は、JA販売店やホームセンターのガーデニング・資材、庭木コーナーにあるものもあります。ほ場で早期発見し、適切な薬剤や防除方法でしっかり発生を予防、ガードできると、農薬散布と言った農作業の回数を減らすことができます。
発生してからの圃場の完全回復は大変なので、適切な土壌管理を心がけ、しっかり防除していきましょう。
若い葉や茎の表面にうどん粉をまぶしたように白いかびが生えるうどんこ病の防除は下記を参考にしてみてください。市販のベニカ、ベニカスプレーなども使えます。
(補足)殺虫剤など、他の農薬について
農家webでは、下記のような害虫別のコンテンツがあります。気になるコンテンツがあれば、ぜひ参考にしてみてください。