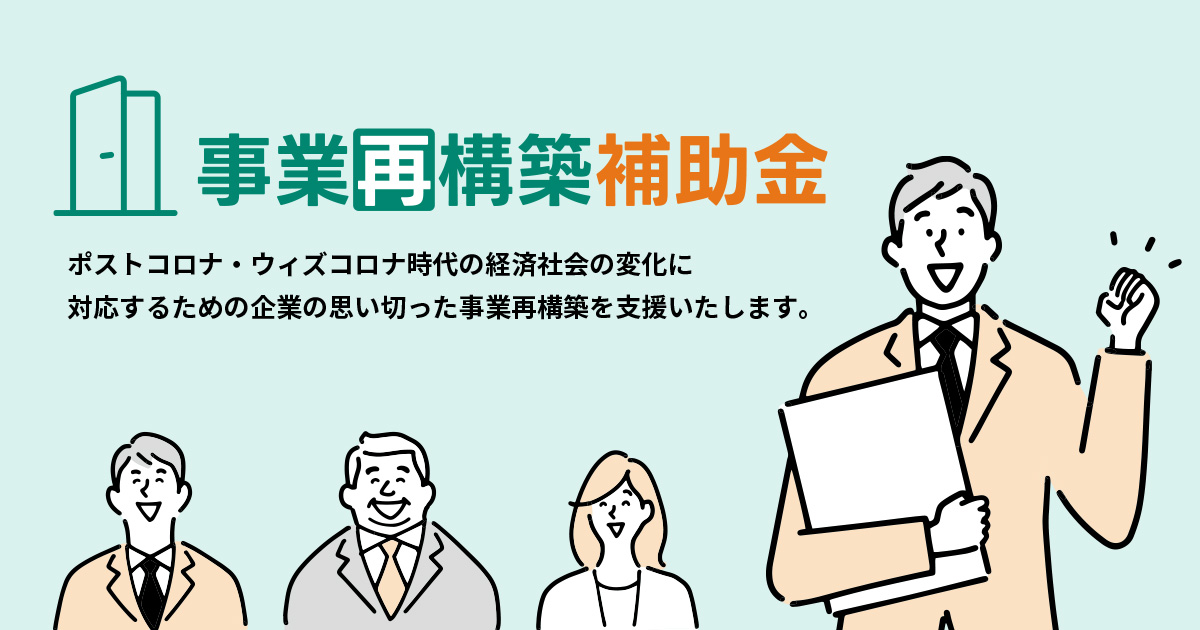営農において、農機具の購入や設備投資は大きなコストとなります。自己資本だけでまかないきれないケースもあるでしょう。農業用ドローン(産業用マルチローター)の導入にあたっても費用の目安をつかんだ上で、活用できる補助金がないかしっかり検討したいところです。
この記事では、農業用ドローン導入時に活用できる補助金について解説します。
※この記事は2023年11月時点の情報です。補助金の内容等の変更や公募が終了している可能性もあるため、必ず各公募の公式ページをご確認ください。
農家webでは、農業で利用できる補助金情報をまとめたポータルサイト「農家web補助金データベース」を構築、運営しています。
農業用ドローン購入に活用できる補助金

農業用ドローンの導入に活用できる代表的な補助金等は、次の通りです。また、都道府県や市町村で独自の支援策を設けていることもあるので、常にアンテナを高く張っておくことも大事です。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) (旧:時間外労働等改善助成金)
「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、 生産性を向上させることにより、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備などを行う 「働き方改革」に取り組む中小企業事業主を対象に、環境整備に必要な費用の一部を国が助成する制度です。
企業規模による労働環境の格差を是正し、働き方改革を幅広く推進する目的があります。
中小企業の事業主が、定められた成果目標の達成に向けて取り組みを実施すると、 成果目標の達成目標に応じて、取り組みのための経費の一部に対して助成を受けられます。
石川県では、「農業用ドローンの活用による農薬・肥料散布での作業負担の軽減と効率化」が好事例として取り上げられています。積極的に活用しましょう。
事業再構築補助金
事業再構築補助金とは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金です。
もちろん、農業者であっても補助金申請をすることが可能です。
ドローン関連の費用としては、ドローンの機体購入やソフトウェア購入、スクール受講料などに活用できると考えられます。
ものづくり補助金
正式名称は「ものづくり・商業・サービス革新補助金」で、中小企業庁が主幹となって実施されています。中小企業や小規模事業者向けの補助金で、生産性向上のための設備投資を促すことが目的のひとつとなっているので、農業用ドローンも対象になります。
補助率は導入費用の中小企業で1/2(小規模事業者で2/3)、上限額は1,000万円とされています。「ものづくり補助金事業公式ホームページ」には、最新の情報が掲載されています。
各地方自治体が独自に公募している補助金
各地方自治体において、独自に公募している補助金もあります。具体例としては下記のものがあります。あなたが営農される地域でも公募されている可能性があるので、よくチェックしましょう。
愛知県田原市 令和5年度スマート農業推進補助金
農業者の所得向上と持続可能な農業を実現するため、ロボット技術やICTを活用して超省力、高品質生産を実現するスマート農業の普及を目指すべく、農業者が自らの営農に使用する目的で購入するスマート農業機器等に対し、購入費の一部を助成するものです。
機械、装置本体や付属品、ソフトウェア・アプリの購入にかかる経費について、1/3以内(限度額50万円)が補助されます。
秋田県秋田市 スマート技術等 導入事業
農業従事者の高齢化、後継者不足に伴う生産・経営技術の継承、労働力不足などの課題解決および農業経営の発展を図ることを目的に実施される事業です。
農林水産省が公表しているスマート農業技術カタログに記載されている、又はこれらと同等以上の機能を有すると認められた機械設備等の購入経費の1/2以内が補助されます。
産地生産基盤パワーアップ事業
産地生産基盤パワーアップ事業とは、その名の通り、収益性向上や生産基盤の強化を主目的とした補助事業です。かつては、「産地パワーアップ事業」という名称で実施されていましたが、内容の拡充などを経て現在のものになっています。
収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、農業者等が行う高性能な機械・施設の導入や栽培体系の転換等に対して総合的に支援します。また、輸出事業者等と農業者が協働で行う取組の促進等により海外や加工・業務用等の新市場を安定的に獲得していくための拠点整備、需要の変化に対応する園芸作物等の先導的な取組、全国産地の生産基盤の強化・継承、堆肥の活用による全国的な土づくり等を支援します
この補助事業では、トラクターやコンバイン、ドローン、農業ロボット(収穫ロボット)等の農業機械の導入に補助金が活用できます。
ただし、支援内容によってはトラクターのリース、買い替え(更新)等に活用できない場合があります。例えば、産地生産基盤パワーアップ事業(新市場獲得対策)のうち園芸作物等の先導的取組支援(野菜)では利用できないと定められています(出典:産地生産基盤パワーアップ事業(新市場獲得対策)のうち園芸作物等の先導的取組支援(野菜)Q&A)。
取組事例も掲載されているので、検討するにあたって参考にすると良いでしょう。
強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ・地域担い手育成支援タイプ)
強い農業・担い手づくり総合支援交付金は、下記を目的に公募されました。
- 産地の収益力強化と担い手の経営発展のため、産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を切れ目なく支援します。
- また、地域農業者の減少や労働力不足等生産構造の急速な変化に対応するための生産事業モデルや農業支援サービス事業の育成を支援します。
しかし、令和3年度でこの交付金事業は終了しています。

令和4年度(2022年度)に「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」から「強い農業づくり総合支援交付金」に変更となりました。
強い農業づくり総合支援交付金
強い農業づくり総合支援交付金は、令和5年3月31日に改正された交付金です。特に生産事業モデル支援タイプは、農業用施設(パイプハウス、耐候性ハウス等)や農業用機械(トラクターや収穫機、播種機、定植機、選別機等)の導入にも活用できるものとなっています。
農林水産省の強い農業支援のパッケージは、基本的に農業用機械や施設(ビニールハウス、パイプハウス等)、スマート農業機器に活用できることが多いので注目しておくと良さそうです。
農地利用効率化等支援交付金
農地利用効率化等支援交付金は、下記を目的に農林水産省が公募しています。
地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、生産の効率化に取り組む等の場合、必要な農業用機械・施設等の導入を支援します。
事業内容は、タイプによってわかれており、下記の3タイプがあります。
融資主体支援タイプ
融資を受けて、経営改善のために必要な農業用機械・施設の導入を支援するものです。
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者等が融資を受け、農業用機械・施設を導入する際の融資残について支援します。また、優先枠を設定し、(ア)ロボット技術・ICT機械等の導入や、(イ)中山間地域等での集約型農業に必要な機械の導入、(ウ)「みどりの食料システム」を踏まえた環境に配慮した営農に必要な機械等の導入を推進します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 1.農業経営基盤強化促進法に定める地域計画のうち目標地図に位置付けられた者 2.実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体 3.実質化された人・農地プランが作成されている地域において、継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者 4.農地中間管理機構から貸借権の設定等を受けた者(地域計画及び実質化された人・農地プランが作成されていない地域に限る) |
| 補助率 | 事業費の10分の3以内 |
| 補助上限額 | 300万円等(必要な要件を満たす場合は600万円) |
融資主体支援タイプのうち先進的農業経営確立支援タイプ
より高い目標をもって、農業経営の主体性を発揮した取組、農業経営体と地域との相乗的発展を目指す取組、より規模拡大を図るための取組等を行おうとする農業経営体に対して、支援を行うものです。
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者等が融資を受け、農業用機械・施設を導入する際の融資残について支援します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 1.農業経営基盤強化促進法に定める地域計画のうち目標地図に位置付けられた者 2.実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体 3.実質化された人・農地プランが作成されている地域において、継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者 4.農地中間管理機構から貸借権の設定等を受けた者(地域計画及び実質化された人・農地プランが作成されていない地域に限る) |
| 補助率 | 事業費の10分の3以内 |
| 補助上限額 | 個人1,000万円、法人1,500万円 |
条件不利地域支援タイプ
経営規模が小規模・零細な地域において、農作業の共同化や農地の利用集積の促進等により、生産性の向上や農作業の効率化等を図り、意欲ある経営体を育成するため、必要となる共同利用機械・施設の導入を支援します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 1.農家3戸以上が構成員に含まれている団体であって、当該農家が全体の議決権の過半を占める等当該団体の事業活動を実質的に支配すると認められる次に掲げる要件を満たす団体 2.要件を全て満たす参入法人 |
| 補助率 | 事業費の2分の1以内、農業用機械にあっては3分の1以内 |
| 補助上限額 | 4,000万円 |
経営継続補助金
2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、農業・林業・漁業者向けの「経営継続補助金」というものもありました。補助率は3/4、上限額は100万円です。
農林水産省のホームページに「逆引き辞典」という補助金を検索できるサービスがあります(融資、出資、税制、優良事例も検索できます)。国や都道府県が行っている農林水産分野の補助金について、目的や都道府県別など条件を絞って検索でき、要件なども確認できます。便利なサービスながら知名度はあまり高くないようなので、ぜひ活用してみてください。
農業用ドローンの免許(資格)取得費用に活用できる補助金

農業用ドローンの資格取得にも補助金が活用できそうです。具体的には「人材開発支援助成金(人材育成支援コース・事業展開等リスキリング支援コース)」などの補助金・助成金が挙げられます。
下の記事に詳しくまとめていますので、ご覧ください。
農業用ドローンを利用するためにかかる費用
費用の内訳は、ドローン機体の購入費用、操縦を学ぶためのドローンスクール受講料、メンテナンス費用、保険料に大別できます。
大事なことは、ドローンを利用する場合にかかる費用と、ドローンを利用しない場合にかかる費用を比較して判断することです。たとえば、ドローンを農薬散布に利用することを考えている場合では、無人ヘリコプターを利用する場合や、手作業による農薬散布の場合などと比較して判断する必要があります。
特に、手作業による農薬散布と比較すると、ドローンを利用した場合は40倍以上の効率ともいわれており、早ければ2年で元をとれる試算もあります。
ドローン機体の購入費用
主な農業用ドローンとして、農薬などを散布する「空中散布用ドローン」、農地や作物の状態をデータ化および可視化する「センシング用ドローン」があります。空中散布用ドローンの方が大型になるため、金額は高くなります。
空中散布用ドローン
農薬・肥料・種子の散布に用いるドローンです。価格はメーカーや仕様によって大きく異なりますが、100万円から300万円くらいが目安です。
センシング用ドローン
機体に搭載されたカメラにより、農地や作物の状態をデータ化および可視化するドローンです。価格はメーカーや仕様によって大きく異なりますが、50万円から100万円くらいが目安です。
ドローンスクール受講料
ドローンの操縦が初めての場合は、ドローンスクールで知識や技術を学ぶ必要があります。また、空中散布用ドローンを使用する場合には、飛行許可申請を経て国土交通大臣の許可承認が必要となり、その際に飛行経験を記載しなくてはいけません。
したがって、現実的にはドローンスクールで飛行経験を積むことが必要と考えられます。ドローンスクールの数は増加傾向にありますが、空中散布用ドローンの操縦を目的としたコースを受講する場合、相場は20万円〜30万円ほどのようです。
メンテナンス費用
ドローン機体の整備点検の費用です。必須ではない場合もありますが、相場としては年1回で数万円くらいのようです。
保険料
必須ではない場合もありますが、賠償保険や機体保険に入っておくと安心です。金額は補償内容によって異なりますが、相場としては数千円から数万円程度です。
まとめ:補助金を受け取るためのポイント
補助金は、申請すれば必ず受け取ることができるというものではありません。書類作成後、審査を経て、採択もしくは承認を得る必要があります。その後も、報告書の作成義務があるものがほとんどです。担当各局と積極的にコミュニケーションをとるなど、粘り強い取組みが求められます。
補助金に興味はあるものの、一連の作業をこなす自信がないという人は、代行サービスを利用するという方法もあります。補助金によっては、販売代理店やコンサルタントなどが、書類作成や申請の代行サービスを行っている場合があります。経験豊富な実績ある代行サービス事業者であれば、採択もしくは承認を得る確率が各段に高まります。自身の状況を鑑みて、代行サービスの活用も検討してみましょう。
補助金は種類も多く、内容も複雑です。しかし、上手に活用できれば金銭的なメリットが得られるだけでなく、農業用ドローンをはじめとする先端技術を積極的に導入する後押しにもなります。あなたも補助金を上手に活用し、攻めの農業経営を展開してみませんか。
農業補助金検索なら農家web補助金データベースが便利
農家webでは、農業で利用できる補助金情報を「農家web補助金データベース」にまとめています。「ドローン」などで検索することもできます。ぜひ、活用してください。