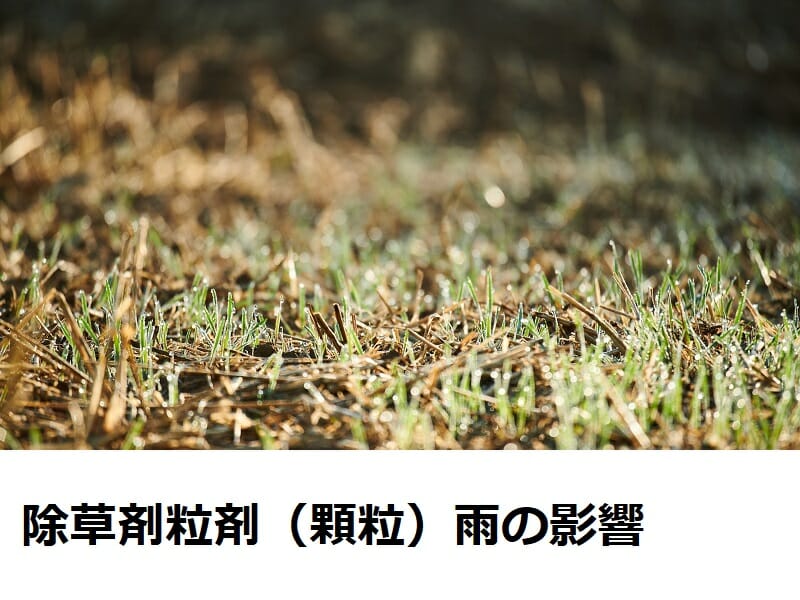顆粒剤の散布のポイント
除草剤には、その効果を最大限に引き出すための散布のポイントがあります。顆粒タイプの除草剤の効果的な散布方法は下記のとおりです。
- ラベルに書かれた散布時期を守りましょう。除草剤は散布のタイミングがとても重要です。
- 土壌処理剤は、乾燥していると効果にムラが出てしまいます。小雨、降雨後の土壌が湿った時に地面に撒くのが一番いいタイミングです。乾燥している場合は水をまいてから散布するとよいでしょう。
- 薬剤は均等に撒くこと。ムラがでるとが残ってしまう可能性があります。
- 土壌処理剤を散布した当日は、散布後は立ち入らないこと。ムラがでやすくなります。
- 土壌処理剤を使う場合に、スギナが大きくなりすぎても草刈りはしないこと。土壌処理剤は雑草が大きくなったら草刈り後に散布することと書かれていますが、スギナは草刈りをすると胞子が飛び散ります。大きくなりすぎたら土壌処理剤は使わず、茎葉処理剤の除草剤を使いましょう。
除草剤散布前に雨が降った場合
顆粒タイプの粒剤は、乾燥が苦手です。そのため雨の後の散布が最適です。
粒剤は、ほとんどが「土壌処理剤」と呼ばれる種類の除草剤で、土壌に粒のままばら撒いて散布します。土壌処理剤は、有効成分が土に吸収され処理層をつくったり、水と一緒に植物の根から吸収されることにより除草効果を発揮します。
そのため、土が乾燥していると土に吸収される前に、風などで飛散(ドラフト)してしまうリスクもあります。雨上がりに撒くことができない場合には、水をまいてから散布します。少ないですが茎葉処理剤にも細粒剤などの顆粒タイプもあります。その場合にも雨の後や、朝露の後などに散布すると薬剤が吸収されやすくなります。
除草剤散布後に雨が降った場合
周りに守るべき作物や植物がない場所や、農耕地以外での使用は雨を気にする必要なく撒けます。しかし、田畑などの周りに守るべき作物や植物がある場合には、雨が降るかどうか、気にする必要があります。
なぜなら、農耕地では処理層ができる前に強い降雨があると、畑地などでは、薬剤が下方向にしみこみ、作物が根から、浸透した除草剤を吸って薬害が生じ、枯れる可能性があるためです。なので、特に農耕地では、散布する日の天気で大雨が予報されている場合は、散布を控えた方がいいのです。
また大雨になると、薬剤が流れて枯らしたくない周りの植物を枯らしてしまうリスクもあります。周辺に枯らしたくない植物がある場合にも大雨には注意が必要です。
除草剤の種類
除草剤には大きく分けて、成長した葉や茎に散布して雑草を枯死させる「葉茎処理剤」と、雑草が生える前や生長初期に、土に散布して雑草の発芽や成長を抑制したり、根から薬剤を吸収させて枯死させる「土壌処理剤」があります。
葉茎処理剤
葉茎処理剤は液体タイプに多い除草剤で、ある程度成長した雑草の葉や茎に散布して、雑草を枯死させます。葉茎処理剤の中には、薬剤が接触した葉や茎だけを枯らす接触型の除草剤と、葉や茎に薬液を散布するだけで、根まで枯らすことができる吸収移行性を持った除草剤があります。
根まで枯らす除草剤には有効成分にグリホサートが入っており、ラウンドアップなどの商品があります。また接触型の除草剤はいろいろありますが、バスタやザクサなどのグリホシネート系の除草剤や、最近よく見かけるお酢の除草剤も接触型の除草剤です。
土壌処理剤
土壌処理剤は、粒剤と呼ばれる顆粒タイプの除草剤に多くあります。
雑草の発生前に土にばら撒くことで、土壌に処理層を形成して、その処理層に雑草の発芽が触れると発芽できずに、雑草の成長を阻害します。また雑草の生育初期に、土にばら撒いた薬剤は、土から水と一緒に雑草の根に吸収され、生育初期の雑草であれば、枯死させることもできます。
非選択性と選択性とは
除草剤には、接触した全ての植物を枯らす「非選択性除草剤」、特定の植物を枯らさず、雑草のみ枯らすことができる「選択制除草剤」があります。
選択制の除草剤は、芝生や田んぼなどに使われ、芝やイネを枯らさず、雑草だけからすことができる便利な除草剤です。
除草剤の使い方や選び方
何年もスギナやドクダミなどの厄介な雑草が生えている場所には、1度除草剤をまいただけでは、なかなか全部枯死させることはできません。成長した雑草に茎葉処理剤を散布し、雑草の生える前に、土壌処理剤を使って防除するなどを繰り返すことにより、駆除することができます。
土壌処理剤のおすすめの商品については、詳しい記事がありますのでそちらも参考にしてください。